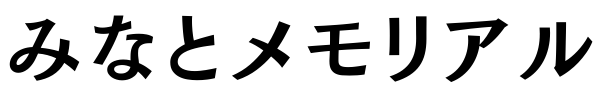先日 せんざん港南台本店(横浜市)様において、お寺様・墓石会社様に向けて『相続とお墓』をテーマにセミナーを開催いたしました。
当日は約20名様にご参加いただき、今後トラブルに合わないように、またできる限り知っておいた方が良い知識について、法律の専門家の行政書士という立場からお話しさせていただきました。
ここではその内容を簡単にご紹介させていただきます。

まず、相続について。
これは家族が亡くなった時に、持っているお金や家などの不動産といった資産がその他の家族(法定相続人といいます)や、遺言があればあればその友人や知人に引き継がれることをいいます。
この相続ですが、原則として亡くなった瞬間に「発生して」何もしなくても、3か月すると「確定」する、ということになります。
大事なのは選択できる、ということではなく自然に発生して、そのまま確定するということです。
それではお墓は相続財産として引き継がれるでしょうか?
ここは相続財産とは異なり、「祭祀財産」として引き継がれることになります。金銭財産とは別です。
祭祀財産の特徴
「祭祀財産の特徴」としては相続人にあたる人が祭祀財産の継承者には必ずしもならないということです。
決め方としては民法897条に明確にきめられていて
①被相続人の指定(口頭でも書面でも、明示的でも黙示的でもOK)
②慣習によりきめる(但し慣習の存在を認めた事例は過去になく、実質不明)
③裁判所による指定←だれも引き継がない場合はこの方法で対所する
という方法により、決められます。
つまり、相続人とは切り離して考えるべき話です。
実務上でも、子供が相続財産はもらうが、お墓や仏壇はいらないという主張されることが結構あります。
では次に相続放棄をした場合の祭祀財産への影響はどうなるのでしょうか。
なおここでの放棄は「裁判上の放棄」をいいます。良く言う話し合いの中で「財産はいらない」となったことを放棄という方がいるのですが、これは本当の意味での放棄ではなく、第三者から相続した負債の返済を迫られても拒否はできません。
結論からいうと相続放棄をしたとしてもお墓(祭祀財産)には影響しないつまり、放棄できないということになります。
最近増えている亡くなった故人の負債が多いので放棄はするのだけど部屋の中にあった仏壇や位牌はどうすれば良いか、という相談もこの考え方で引き取っても大丈夫です、という回答をしております
放置されたお墓
次のテーマとして墓地の管理料が中々徴収できない、お墓が放置されているというお話に触れてみたいと思います。
昨今、お墓を管理していた方がお墓に来なくなったこともあり実際誰が管理していたかかわからない、管理者が亡くなっていてその後誰に引き継がれたかわからない、ということもあるかと思います。
この場合対応はどうすれば良いでしょうか。
1つ覚えていただきたいのが、管理料が滞納されたり、連絡しても返事がないからといって強制的にお墓撤去及び合祀にすることはできません。
日本の法律で「自力救済の禁止」といって勝手撤去することが禁じられているからです。
その際に確認してほしいのが、「墓地の管理使用規則」になります。
こちらを作成していますか?
これは使用者と霊園側のかなり強い「契約」になるのでこれがない場合は早急に作ってください。
ある場合でも管理料の徴収方法や計算方法、誰が払うなどを見直して使えるものにされることをおススメします。
ここでこの規則をもとに、法的根拠を示したうえで墓地の管理規約に基づいて、規約上の「契約の解除」に当たることを示してまず契約の解除を行ってください。
そして、その契約の解除に基づく、現状回復義務すなわちお骨の改葬や合祀お墓じまいの工事を法的な順序に基づいて進めていく・・・
こんな手順を踏んでいただければと思います。
大事なのは、使用者と共通のルールとなる「規則」これをちゃんと整備して手順を明記しておくということです。
昔作ったフォーマットのまま、そのまま今まできているという方はこれかなり危険が潜んでいることが多いです。
一度専門家を挟んで今の時代に合ったようにしっかりと見直してアップロードされることをおススメします。
私達は墓地埋葬に関する法律の専門家として規約などもサポートできますので
もし、気になったことがあればご相談いただければと思います。

クルーズグループでは、終活や相続に関するご相談を受け付けています。
お客様ひとりひとりのお話をじっくり丁寧に伺い、遺言書の作成から医療・介護時のサポート、葬儀・埋葬の手配に相続に関する諸手続きに至るまで、私たちが誠心誠意お手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。↓
☎ 050-5482-3836